目次
はじめに
現在日本国内では、少子化により学校の合併や廃校が増加している。また、子どもに対する教育方針も大変シビアな時代となっていると感じられる。みなさんも学生の立場として、感じている悩みや不安もあると思う。将来的にも、教育制度が整っていなければ子どもを持つことさえ不安を感じてしまう。実際、そのように感じている家庭は少なくはないだろう。
そこで、私が高知に来てから感じ取った、高知の教育の在り方を語っていきたい。それは、これまでの日本の教育の先駆けとなる要素が、またこれからの日本の教育の問題解決の鍵がありふれる、そんな教育領域のロマンがこの記事では次々と露わとなっていく。
高知教育の歴史

高知の教育の始まりは、1874年に設立された「陶冶学舎」からである。陶冶学舎とは、現在の高知大学教育学部の起源であり、陶冶学校、高知県高知師範学校と改称されていった。また、1878年には高知県女子師範学校が設立され、はやくも県内で男女とも勉学に励むことができた。その後は、合併や新たな学部学科・小中学校の設置を繰り返し、現在に至る。
また、高知県立大学も高知にとって語らずにはいられない重要な歴史を持っている。高知県立大学は、1944年に高知県立女子医学専門学校として設立された。また、1956年に家政学部の中に看護学科を設置し、日本で最初の4年制看護学教育を開始した大学であるとされた。その後、文学部(後の文化学部)、社会福祉学部、健康栄養学部、大学院を新設し、2011年に男女共学となり、現在の高知県立大学と校名も変更された。
こういった歴史から、高知の教育は男女の教育の機会をはじめとして、日本の近代的な教育の整備に即座に対応し、時代に順応した教育を進めていくことができたのである。
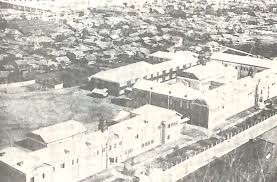






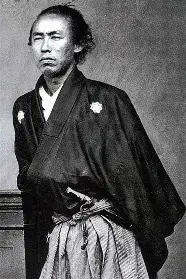


コメント