オタクは激怒した。
目次
「高知にはカツオと龍馬しかない」?
坂本龍馬は言わずと知れた高知出身の偉人である。社会科の教科書に留まらず、クイズ番組やゲーム、アニメなどにもよく登場し、大河ドラマでは2回も主役を飾っている。没後150年を過ぎた現在でも坂本龍馬は人気である。
いや、人気どころの騒ぎではない。
龍馬像の前では多くの観光客が像とともに写真を撮影しているし、お土産ショップには龍馬をモチーフにしたグッズがずらりと並んでいる。観光客だけでない。空港ができれば「高知龍馬空港」、マラソン大会を開けば「龍馬マラソン」、観光パスポートを作れば「龍馬パスポート」――高知の人は何かにつけて龍馬の名前を入れたがる。
しかし、あまりにも坂本龍馬が押されすぎている現状について、この一介の歴史オタクは眉をひそめている。高知の人たちに高知と言えば?と聞いてみても、自嘲気味に「高知にはカツオと龍馬しかないき」と言うことも少なくない。現地の人ですらこの認識なのだ。これはいけない。
これでは観光客や県外からやってきた人たちに、坂本龍馬以外の高知の人物を知られないまま終わってしまうのではないか?
そんなことはさせない。そんな歴史オタクの怒りで書き上げられたのがこの記事である。
とはいえ、私も詳しくない時代には本当に詳しくない。例えば戦国時代のことを書いたら戦国時代オタクから指摘が針山地獄ができるくらい飛んできそうなので、ここは比較的知識がある幕末の高知・土佐(奇しくも龍馬と時代が被っている)の人物を取り上げることにする。
そしてこの記事は単に人物を取り上げるだけに留まらない。人物ゆかりの地に訪れる、いわゆる聖地巡礼の記事でもある。「車必須」と言われがちな高知の観光地だが、免許も車も持っていない人でも公共交通機関を用いて訪れる方法があることも伝えたい。今回訪れた“聖地”はどちらも高知市から日帰りで行ける距離にあるので、高知県外の方はもちろん、高知県在住の人々の小旅行にも、「高知トラベル」におすすめのスポットだ。
なお記事に掲載されている画像について、人物の写真はパブリックドメインとなっており、それ以外の画像については私自身や同行した友人が撮影した写真(掲載許可取得済)である。
〇〇の写真!?中岡慎太郎(なかおかしんたろう)

中岡慎太郎(なかおかしんたろう)は幕末の志士である。現在の高知県安芸郡北川村の大庄屋の家に生まれ、土佐勤王党(尊王攘夷を掲げた結社)に加入。のちに開国論に転じ、犬猿の仲と言われた薩摩藩と長州藩を和解させ薩長同盟の締結を周旋したことが有名である。また、それぞれ太宰府と洛北に追いやられていた三条実美と岩倉具視、かつてバッチバチに政局争いを行った公家二人も結び付けた。この二人は明治になるとそれぞれ太上大事、右大臣のポストに就く超重要人物であり、これは明治新政府にも大きな影響を与えただろう。
慎太郎は人と人とを結びつけることで、歴史という大舞台を動かした男なのである。
しかし巷では「龍馬と一緒に暗殺された人」と、同じく近江屋事件で殺された山田藤吉とどちらか分からない呼ばれ方をされることもしばしば……(というか龍馬は即死したが、中岡は瀕死の状態で逃げ二日後に亡くなったこともあまり知られていないのでは)。これは非常に悲しい。
勇ましい顔付の写真が残る中岡慎太郎だが、彼には意外な姿を映した写真も残っているのだ。
意外な姿……それは笑顔の写真である。それがこちら。

うわーッ、めっちゃいい笑顔ー!!!!!
「笑顔なんて普通じゃない?」と思うかもしれないが、時は幕末。今のようにスマホですぐパシャパシャ撮れる時代ではない。まだ写真機が日本に入ってきて間もない時代、ここまで満面の笑みを写した写真を残した人がいるだろうか?なおこの写真は、日本初の笑顔の写真と言われているらしい。
激動の幕末を生き、その果ての明治を見る直前で非業の死を遂げた慎太郎だが、日本のために東奔西走していた彼にもこのような笑みを浮かべるひと時があったのだ。この笑顔がきっかけで中岡慎太郎に興味を持ったという人も、きっといるのではないだろうか。
中岡慎太郎の聖地―北川村 中岡慎太郎館―
慎太郎の出身地・北川村(きたがわむら)は、高知市から約60kmのところに位置する。その北川村にある中岡慎太郎館(なかおかしんたろうかん)は、慎太郎の生涯や功績を紹介するだけでなく、慎太郎やゆかりの人物に関する資料を展示する記念館だ。
JR高知駅からJR土讃線土佐山田(とさやまだ)行に乗って東に15分ほどでJR後免(ごめん)駅に着く。後免駅で土佐くろしお鉄道ごめん・なはり線の奈半利(なはり)行に乗り換え、そこからおよそ1時間のぶらり電車旅だ。道中では阪神タイガースのキャンプが行われることでも有名な安芸市営球場(安芸タイガース球場)を見ることもできる。
ところで、ごめん・なはり線の各駅には高知県出身の漫画家・やなせたかし先生がデザインしたキャラクターたちがいるするのだが、私の推しは、終点の奈半利駅のキャラクター「なはりこちゃん」である(画像左)。糸目がとてもかわいらしい。
 左)奈半利駅のキャラクター「なはりこ」ちゃんの画像
左)奈半利駅のキャラクター「なはりこ」ちゃんの画像
(右)奈半利駅と北川村をつなぐ北川村営バスの画像
ごめん・なはり線の終点・奈半利駅に到着したら北川村村営バス(画像右)に乗り換え、で柏木(かしわぎ)というバス停まで向かう。その他の停留所には、モネが愛した風景を再現した北川村「モネの庭」マルモッタン最寄り・モネの庭や、日帰り入浴も楽しめる北川村温泉ゆずの宿最寄り・小島もある。ここから分かるように観光客に嬉しい交通機関であることはもちろんだが、村民の生活に必要不可欠な施設に近い停留所も多く、村民の足としても活躍していることが伺える。道中には慎太郎が庄屋見習い時代に栽培を奨励した柚子の木が、数多く植えられているのを見ることができる。おそらく今想像されているであろう本数の100倍は多い。柚子だらけ。マジで柚子だらけ。
柏木でバスから降りれば、目的地である中岡慎太郎館は目の前である。
 中岡慎太郎像と中岡慎太郎館
中岡慎太郎像と中岡慎太郎館
中岡慎太郎館は、慎太郎の顕彰活動を行ったり、慎太郎関連の人物の資料を集め展示する記念館である。
1階では中岡慎太郎の生涯を紹介している。パネルは時系列で展示されており、若き頃の慎太郎に影響を及ぼした人物や、慎太郎の活動に関係する人物も紹介されているので非常に分かりやすい。また、パネルだけでなく映像もあるので、「歴史は苦手!」「全然わからない!」という人でも楽しんで見て学ぶことができる。
2階では慎太郎や慎太郎と交流のあった人物たちの資料が展示されている。慎太郎たちが暗殺された際に血痕が残った屏風の複製や、実際に慎太郎が着用していた袴など、貴重な資料を見ることができる。年数回行われる企画展の会場もこの2階にある。私は今回2025年2月に訪れたのだが、木でできたひな人形や、刀の展示が行われていた。
さて、旅には空腹がつきものだ。周囲に軽食が買えるコンビニやスーパーはないが、中岡慎太郎館を出て徒歩1分、走れば30秒の位置にある慎太郎の顕彰会店舗内にある「慎太郎食堂」ではお昼ご飯や軽食を食べることができる。今回、私は日替わりメニューである「きたがわランチ」のスタミナ肉豆腐をいただいた。
 スタミナ肉豆腐
スタミナ肉豆腐
こういうのがいいんだよ、こういうのが
お分かりいただけるだろうか、このTHE・家庭料理感。メニューにあったコンセプトには「『ふつうに美味しい』お家ごはん」と書かれていたが、その通りである。100万ドルの夜景を臨むレストランのコース料理のような、特別な美味しさはない。けれども、のどかで自然豊かな北川村の昼下がり、奈半利川の流れが心地よい中で食べるなら、こういう馴染みのある料理が一番なのではないだろうか。味も「ふつうに美味しい」。デザートとして、白玉ぜんざいゆず風味とゆずジュース(アイス)もいただいた。ぜんざいの中に柚子の皮が入っており、香りを存分に楽しむことができる。またここの店主さんは茶道の師範でもあるらしくメニューには抹茶セットも用意されている。次回訪れた際はぜひいただきたい。
周囲には慎太郎の生家や、慎太郎の功績を記した長い石碑が設置された中岡慎太郎記念公園、幼い頃の慎太郎が飛び込んで遊んでいたという巻の渕を見ることができる展望所がある。どれも歩いて5分もかからないので、昼食後の軽い運動やバスの待ち時間にいかがだろうか。
中岡慎太郎館に行くことで慎太郎について学べるのはもちろんだが、慎太郎を育み、庄屋見習いとして慎太郎が育てた北川村の風景を楽しむことができる。一周見て回ってもかかる時間は長くても二、三時間で、同じ日に別の場所を見て回ることもできる。毎年11月には「慎太郎とゆずの郷祭り」も開催されており、当日は各施設の入場料などがお安くなるだけでなく、北川村の魅力にさらに触れることができる。
歴史好きだけでなく、柚子が大好きな人、北川村に興味がある人、ガッツリではなく適度に自然に囲まれたい人にもおすすめだ。













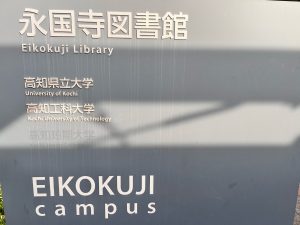
コメント