まだ知らない世界の料理に挑戦!
日本ではまだあまり知られていない世界の料理を、あなたは作ったことがありますか?
私は今回「異文化の食」をテーマにしようと思ったとき、最初は近くの海外料理店に行ってみようと考えました。
しかし、異国の料理を扱っている飲食店に行って食べるだけでは、レシピも作る手間も、その国の文化も、料理の背景も知ることはできない。やっぱり、実際に作ってみて手を動かすことでこそ、料理の背景や文化をより深く感じられるのではないかと思ったのです・・・
…と、ちょっと御託を並べましたが、実際には自炊のレパートリーを増やしたかったのです。それと、異文化に興味があるのはもちろんですが、単純に食べるのが大大大大好きだからという理由も大きいです🤤🤤🤤
そこで今回の高知トラベルでは、高知にいながら世界を旅する気分で、
①ラサーリ(マダガスカル)
②シャモ・ケワ・ダツィ(ブータン)
③リニヴィエ・ガルプツィ(ロシア)
④イカン・サンバル(インドネシア)
の4つの料理に挑戦してみることにしました!ネットスーパーで本格的な食材を取り寄せることもできますが、せっかくならこの記事を読んだ人も挑戦できるよう、比較的簡単で、日本のスーパーでそろえやすい食材で作れるレシピを厳選して、ちょっとした文化の話も交えて紹介します♪
本記事は「レシピ➡食のミニコラム➡感想」の順で進みます😊異文化に興味がある方はもちろん、料理のレパートリーを増やしたい方や、食べるのが好きな方、はたまた読む専の方も、作ったみたり、初めて知ったなーへーと思ったり、少しでも楽しんでいただければ幸いです!O(∩_∩)O♪ それではLET’S COOK!!
1.ラサーリ(トマトのシンプルサラダ)《マダガスカル》
└ご飯とともにある暮らし
2.シャモ・ケワ・ダツィ(きのことじゃがいものチーズ煮込み)《ブータン》
└ブータンの代表料理「エマダツィ」
3.リニヴィエ・ガルプツィ(怠け者のロールキャベツ)《ロシア》
└戦火を越えて受け継がれた家庭料理
4.イカン・サンバル(魚(あじ)のサンバルソースがけ)《インドネシア》
└食卓に欠かせない「サンバル」
5.おわりに
ラサーリ(トマトのシンプルサラダ)

材料(2人分)
・トマト:中2個(一㎝サイコロ切り)
・青ネギ:2本(小口切り)
ドレッシング
・ライム汁:1/2個分
・ショウガ:小さじ1/4(すりおろす)【チューブ生姜を使用】
・ホットソース(タバスコ):好みの量
・塩、コショウ:適宜
作り方
①ドレッシングの材料をすべて小さな器に入れて混ぜる。
②トマトと青ネギをボウルに入れてドレッシングをかけ、ホットソース、塩、コショウで味を調える。
・マダガスカルの人々は、基本的に一日三食すべてでご飯を食べるため、お米の存在は欠かせません🍚日本もお米が主食ですが、日本よりも圧倒的にお米を消費しています。主に白米と赤米の二種類があり、特に赤米はおかゆにして食べることが多いそう。北部では白米をココナッツと少量の塩で炊くこともあり、南部ではサツマイモやキャッサバも主食として食べられます。
味付けは塩を基本に、トマトや玉ねぎで風味を加えるのが定番。にんにく、胡椒、生姜、カレー粉などを使うこともありますが、全体的にあっさりとしていて辛すぎないものが多いです♪
特に面白いのは「ラヌアパング(おこげ茶)」という飲み物!ご飯を鍋で炊いたあと、底にできたおこげ(アパング)に水(ラヌ)を注いで沸かし、香ばしい香りのお湯を飲む習慣があります。炊飯器があってもあえて鍋で炊く家庭もあるほど!おこげの香りが懐かしく、来客へのおもてなしにも出されるそうです🍚🍵
感想
★★★☆☆(3/5)
・これはすっっっっぱい!!!!すっぱいです!!はじめ味見した時分量間違えてないか確認しました。トマトにも酸味があるのですっぱいの好きな私でも結構すっぱかったです!🍅🍋🟩
ですが、エマダツィと一緒に食べてみると、このこってり系にすごく合う!ライムの爽やかさが口の中に広がって、青ネギの香りがアクセントになって、エマダツィとラサーリの無限ループです。口がとってもさっぱりする!生姜とタバスコが後からピリッと来るのもいい感じ。メインで食べるのではなく、こってり系メインがあることによって本領を発揮するタイプです。ライムの代わりにレモン汁でも良さそうです!
シャモ・ケワ・ダツィ(きのことじゃがいものチーズ煮込み)

材料(2人分)
・じゃがいも:2個
・きのこ類:500g【今回はエノキ、まいたけ、しめじを使用】
・玉ねぎ:1/2個(薄切り)
・にんにく:1かけ(みじん切り)
・しょうが:1かけ(みじん切り)
・ミックスチーズ:100g
・水:100cc
・サラダ油:大さじ1
・一味唐辛子:小さじ1【輪切り唐辛子も追加(お好みで)】
・塩:小さじ1
作り方
①じゃがいもをゆで、2cmの角切りにする。
②鍋に材料をすべて入れて、弱火で混ぜながら15分煮込む。(じゃがいもが柔らかくなり、チーズが溶けてもたっとすれば完成)
・「エマダツィ」というのは唐辛子のチーズ煮のことで、ブータンの日常食です。今回のレシピでは一味が使われていましたが、本場ではピーマン大の唐辛子を一緒に煮るので激辛!!旬の夏は青唐辛子、それ以外の時は乾燥した赤唐辛子を主に使います。唐辛子は険しい山岳地域でも比較的育てやすいこと、ビタミンCを豊富に含むこと、そして海から遠い土地において塩代わりのように食を進めるといった理由から、ブータン料理は唐辛子尽くしなようです。
「エマダツィ」はエマ(唐辛子)とダツィ(チーズ)を煮たもの、ケワダツィはケワ(じゃがいも)とエマとダツィを煮たもの、シャモダツィはシャモ(きのこ)とエマとダツィを煮たもの。今回のレシピは「シャモ・ケワ・ダツィ」なので、シャモ🍄🟫とケワ🥔とエマ🌶️とダツィ🧀を煮たものということですね!単純だけどなんだかややこしい!!😭
すべてのベースにエマダツィがあり、とにかく「唐辛子とチーズと何か」というパターンが常。時々チーズの入らない料理があるものの、唐辛子からは逃げられないようです。辛いもの好きにはたまらない国!ブータン!!
感想
★★★★★(5/5)
・調味料が塩だけで正直とても不安だったのですが、本当においしい!!!チーズが伸びてとろとろでほっぺた落ちます!!😭塩だけでなんでこんなにおいしいのかわからない。きのこのうまみ?????じゃがいもがすごくほくほくで、チーズのまろやかさ、ピリッとした唐辛子の辛さとよく合っていました。チーズと唐辛子、間違いないです🧀🌶️個人的には追加で唐辛子を入れたのは大正解でした!シンプルなのに味に奥行きがあって、一口食べるごとに満足感がすごい。
パンに乗せたあと追いチーズしたり、ご飯と一緒に食べたりしましたが、パンにもご飯にもめっちゃ合います。唐辛子が「塩代わりのように食を進める」の意味を実感しました🥰❤️これは大好き。これからも絶対作りたい一品です!
リニヴィエ・ガルプツィ(怠け者のロールキャベツ)

材料(4個分)
・キャベツ:200g(「怠け者」なので、市販のカットキャベツでもよい。)
・牛ひき肉:150g
・米:30g(炊いたお米なら70g)
・塩:1g(小さじ1/5ほど。親指、人差し指、中指の3本でつまんだ量。)
・こしょう・ブイヨン:各適量(市販の固形ブイヨン1個を湯に溶かしたもの)
・キャノーラ油:大さじ1
作り方
①米を洗って鍋に入れ、少量の湯で煮る。表面が透明になったらざるに上げ、冷ます。
②キャベツをせん切りにする。ボウルにひき肉、⓵の米(粒がなくなるようしっかりつぶす)、キャベツを入れる。
③塩、こしょうをふり、手でよく混ぜる。
④生地を4等分にし、ピロシキの形にする。(※ピロシキ:ロシアの伝統的な家庭料理。握りこぶしと同じくらいの大きさで、ラグビーボールのような形。)
⑤フライパンを火にかけて油をひき、⓸を薄く焼き色がつくまで焼く。
⑥ブイヨン(または湯)をガルプツィの高さ3/4ほどまで入れる。
⑦蓋をして、弱火で20分ほど煮込む。
・20世紀に起きたロシアの政治的・経済的な変化は、家庭料理にも大きな影響を与えました。第一次世界大戦やロシア革命、さらには第二次世界大戦などの影響で、人々の生活水準が大きく下がり、ロシア料理も次第に簡素化されていきました。限られた材料で作れるよう工夫された、手軽で安価なレシピや調理法が広く普及したのです。その中で、ソ連時代に人気を集めたのが、手軽に作れる「リニヴィエ・ガルプツィ(怠け者のロールキャベツ)」です。
ひき肉・お米・キャベツを混ぜ、ピロシキのような形にしてブイヨンで煮込むだけ!さまざまな作り方があるそうですが、どの作り方でも大切なのは、 ガルプツィ(ロールキャベツ)はキャベツ料理、だということ!主役のキャベツの量は、他の材料と同じか、それ以上が理想だそうです。
寒冷なロシアでは各家庭にストーブがあり、料理にもそのストーブが活躍しました。上でパンを焼いたり、鍋を乗せて煮込み料理を作ったり…さらに、ストーブの上には人が寝られるスペースがあったそうです!🔥そんな暮らしの中から、弱火でゆっくり煮込むスープやガルプツィのような温かい煮込み料理が育まれました。忙しいお母さんたちは、料理を煮込んでいる間に別の家事をこなしていたのかもしれませんね😊🍲
感想
★★★★☆(4/5)
・料理名に「怠け者」とつくだけあって、簡単に作れてよかったです♪はじめキャベツ入りハンバーグみたいになってしまうのではないかと不安だったのですが、キャベツの分量の方が多いためか、味は完全にロールキャベツです!!むしろキャベツが多すぎて本当に混ざるのか心配になりました(T_T)
普段の料理ではつなぎにパン粉を使うことが多いので、ロシアではお米を使うことを知って驚きましたが、食べてみるとお米効果なのか、しっとり、ふわふわ!!今度からつなぎにお米積極的に使います。ありがとうガルプツィO(∩_∩)O♪
キャベツの甘みとひき肉のうまみが煮込むことでしっかり出ていて、全体的にやさしい味わい。味付けも薄そうだなあと思っていましたが、じっくり煮込んでいるためか全くそんなことなかったです!ケチャップとタバスコをつけて食べたら最高でした。ちなみにキャベツは今回粗めに切ってしまって崩れやすかったので、むしろカットキャベツの方がおすすめかもしれません。
イカン・サンバル(魚(あじ)のサンバルソースがけ)

材料(2人分)
・あじ:2尾【開いてあるアジを使用】
・ターメリック:小さじ1/2
・塩:少々
・バジル:1枝【チューブバジルを使用】
・油:大さじ3
サンバルソース
・ミディトマト:1個
・干しえび:大さじ1
・にんにく、しょうが:各1片
・赤唐辛子の小口切り:1本分
・塩:小さじ1/2
・砂糖:小さじ1
・油:大さじ2
・パクチー:少々(飾りなのでお好みであってもなくても)
作り方
①あじはエラと腹ワタ、ゼイゴ(アジの尾に近い側面に一列に並ぶ刺のような鱗)を除いて洗って水気をふき、腹にバジルを詰め、塩とターメリックを全体にまぶす。フライパンに油を熱して入れ、ふたをして両面をじっくり焼いて火を通し、最後にふたをとってパリッと焼く。
②サンバルソースを作る。ミディトマト5mm角に切る。干しえび、にんにく、しょうがはみじん切りにする。小さいフライパンにすべての材料を入れて炒め合わせる。
③器に⓵のあじを盛り、⓶のサンバルソースをかけ、パクチーを飾る。
・赤や青の唐辛子やトマト、紫色のエシャロットなどをベースに魚介の風味を効かせた甘辛いチリソース「サンバル」は、インドネシアの食卓に欠かせない調味料です。サンバルで味付けした「ナシゴレン」は日本でもおなじみですね!サンバルは料理の種類に合わせて市販品を選んだり、家庭で手作りすることも!辛さの調整はサンバルで行うのが基本で、辛いものが得意な人はなんと揚げ物と一緒に生の唐辛子をそのまま食べることもあるそうです🌶️✨
食事は1日3回で、1日の始まりを大切にしているため、最もしっかり食べるのは朝食!☀️夕食は家族や友人と過ごす大切な時間であり、インドネシアでは大家族が多いため、大勢で食卓を囲むことが一般的♪大皿に盛られたおかずを、好きなだけ自分の皿に取り分けて食べます。食卓を囲む時間、にぎやかで温かい食卓そのものが、人々にとっての幸せなのかもしれません👨👩👧👦❤️
感想
★★★★☆(4/5)
・味はすごくおいしかったのですが、他の料理に比べると魚をさばく手間(今回はゼイゴを取ったただけですが)や、ターメリックをまぶす手間があったので★4です😭とにかくサンバルソースがおいしすぎる!!何にかけてもおいしいでしょう。こんなものは。大容量をストックしたい^.^
詰めたバジルのいい香りがして、魚にサンバルソースのピリ辛で甘味のある味が絶妙にマッチします!今回はあじを使用しましたが、「イカン」は「魚」を意味するようなので、あじでなくてもよさそうです。
サンバルソースはスイートチリソースに魚介のうまみが加わった感じで、私はこっち派です!🤤ターメリックをかけすぎたかもと思ったのですが、きれいな黄色になって、結果的においしかったです♪
おわりに
・今回の高知トラベルでは、あまり聞きなじみがないであろう料理を4つ紹介しました!新しく学んだことも多くあったし、自炊のレパートリー増えましたO(∩_∩)O♪そして、世界のいろいろな料理を作ってみて、どの国の料理にも、その土地の暮らしや文化がちゃんと息づいているということを感じました👨🍳
「食文化」という言葉は1980年代になって広まった比較的新しい言葉ですが、実際はずっと昔から人々の暮らしの中で受け継がれてきたものだと思います。
文化人類学者の石毛直道さんは、食文化を「食料の生産や流通、栄養、食べ方や体のしくみに関する考え方など、食にまつわるあらゆる文化的な側面」と説明しています。そして食行動には、料理のような物質的な側面と、みんなで食卓を囲む社会的な側面があるとも言っています。
そして、人が他の動物と異なる点は、自然からの食べ物を得ただけでなく、より安全で安心な食べ物を確保するために火を使う知恵を身につけたことにあります。私たちの先人たちは、加熱することで食べられないものを食べられるようにし、さらに保存や調理の知恵を発展させてきました。
高知の郷土料理の一つ「さば寿司」もその一例です。塩漬けや酢でしめたサバを使い、もともとは魚を長く保存するための工夫から生まれました。山間部では海が遠く、運ぶあいだに魚が傷まないように酢でしめて寿司にしたのが始まりとされています。こうした工夫の積み重ねが、今の私たちの豊かな食文化へとつながっているのだと思います。
高知には、カツオのたたきや皿鉢料理をはじめ、太平洋と四国山地に囲まれた地形を生かして、海の魚と山の野菜・薬味を組み合わせる料理が多く見られ、自然や人のつながりとともに育まれた独自の食文化があります。同じ日本の中でも、地域ごとに食の特色があるのだと感じると、それらもまた、世界の多様な料理と同じように人々の暮らしの結晶なのだと実感します。
人は「食べること」を工夫してきたからこそ、今の豊かな食生活がある。そんなことを感じながら、これからも多様な食文化に触れていきたいです🍴🌏
・萩野恭子,2022,『おうちでできる世界のおそうざい』,東京:株式会社河出書房新社.
・本山尚義,2017,『全196ヵ国 おうちでつくれる世界のレシピ』,兵庫:株式会社ライツ社.
・ヴィタリ・ユシュマノフ,2021,『はじめてでも美味しく作れるロシア料理』,東京:株式会社世界文化ブックス.
・佐藤政人,2021,『驚きの組み合わせが楽しいご当地レシピ 304 世界のサラダ図鑑』,東京:株式会社 誠文堂新光社.
・岡根谷美里,2025,『世界のお弁当とソトごはん』,東京:株式会社 三才ブックス .
・鈴木志保子,2021,『日本から見た世界の食文化-食の多様性を受けいれる-』,東京:第一出版株式会社.





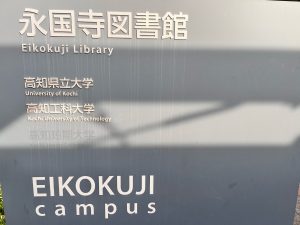



コメント