・土佐弁とは、高知県を始め、高知県(旧土佐国)の中部・東部で話される日本の方言である。四国方言に分類される。高知県西部の方言は中部・東部との違いが大きく、西側は幡多弁、東側は土佐弁と呼ばれる。
・土佐弁が話される高知県とは
日本の四国地方に位置する県。県庁所在地は高知市。山地率は89 %と全国一位。人口は約66万人。 坂本龍馬や吉田茂などの、数多くの先人・偉人を輩出してきた歴史と風土がある。観光スポットとして日本最後の清流といわれる四万十川のほか、水辺利用率全国一の仁淀川など四国山地に源を発する清流が多く流れる。室戸岬・足摺岬・龍河洞・四国カルストなど多くの天然の観光資源を有する立派な県。





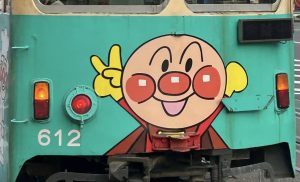


コメント