高知には、歴史的な建物や物がたくさんあります。なかでも有名なのが高知城です。
高知城は、高知にあるお城で、城跡は国の史跡にされており日本100名城にも選ばれています。高知城は、1611年に初代藩主山内一豊によって建てられました。山内一豊は、織田信長・豊臣秀吉・徳川家康に仕えた武将で、徳川家康から関ヶ原の戦いの後の論功行賞で、土佐一国9万8,000石を与えられることになりました。そこで建てられたのが高知城です。
度重なる水害に苦しめられましたが、治水の工事や、職人の努力もあり1601年(慶長6年)に築城が開始され、1611年(慶長16年)に完成しました。
日本の城のうち現存12天守と呼ばれている江戸時代に建てられた天守が現存している城の中で天守と本丸御殿の2つ両方ともきれいな状態で残っているのは高知城だけであり、それが高知城の最大の魅力です

高知城の重要文化財
高知城には、15の重要文化財があります。
それはいったい何なのか、どういう役割なのかということを今から紹介していきます。
・天守
城主の権威のシンボルを表す建物
お城の最重要部である本丸に建てられている。
・懐徳館
城内に建てられた御殿の一つで城主が平時居住するのではなく正規の対面所として作られた
・納戸蔵
物を保管しておく場所として使われていた
・黒鉄門
近世城郭の櫓門(やぐらもん)であり、扉は鉄板や鉄鋲で補強され,より頑丈に作られている。
扉のなかに筋鉄をいれ、外観上は漆喰塗の壁が見られずすべて板張りで黒く仕上げられていることから黒鉄門という名前で呼ばれている
・西多聞 ・東多聞
防御の要所となっている
特に西多聞は単なる防御施設ではなく、戦いに備えて武器や弾薬などを保管する倉庫としても活躍しました。
・詰門
城の防御機能を強化するために設けられた重要な門です。本丸へ直接入られる最後の関門として機能しました。詰門の近くされて狭く設計されており敵の動きを制限するように作られています。
・廊下門
単なる通路としてではなく、城の構造上防衛や、監視の観点から特別な役割を持っていました。
・追手門
城の正面であり、敵が攻めてきた際に最初の防衛ラインとして機能しました。また、防衛だけでなく、城の象徴としても重要な役割を果たしています。
・天守東南矢狭間塀
天守に行くための通路に作られている門で、矢狭が作られています。
矢狭とは門に設けられた小さな隙間のことで、敵に対して矢や鉄砲を撃つために作られました。
・黒鉄門東南矢狭間塀
高知城の入り口である重要な門に設置された矢狭のこと
・追手門西南矢狭間塀 ・追手門東北矢狭間塀
追手門の西南・東北にある矢狭門のことで、最初の防衛ラインで守りきるために機能しました。

高知城の天守からの景色
高知城の天守からの景色も高知城の魅力の一つです。
高知城の天守からは、高知の街を360°一望することができます。
また、景色だけでなく、追手門やしゃちほこもみることができます

まとめ
高知城は、重要文化財があったり、国の史跡にされており日本100名城にも選ばたりなど日本のお城の中でも有数な歴史ある建物です。
天守閣からの景色は絶景で一度は見てもらいたいです。
また、期間限定でライトアップをしているのもぜひ見てください。




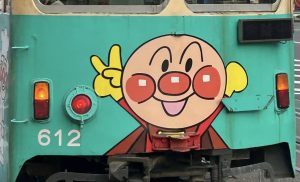


コメント